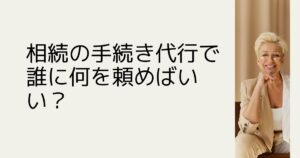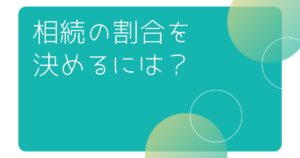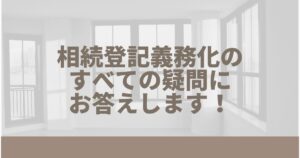「遺留分って何ですか?」
「遺留分を侵害しないようにする生前対策はありませんか?」
「遺留分の相続生前対策って基本的に立証されるの?」
このように疑問を持つ方も多いでしょう。
そこでこの記事を読むことで全ての疑問が解決できるようにスッキリまとめてみました。
この記事を読み終わるまでには5分もかからないでしょう。
たったの5分で相続生前対策を5つも知れるとてもお得な記事となっています。
出来るだけ例を使ってわかりやすくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
遺留分とは?

遺留分とは、各相続人に与えられる最低限保証される、相続できる権利のことです。
例えば、亡くなった人が長男に相続財産全部相続させると言った内容の遺言書を書いたとします。
それが例え亡くなった人の意志だとは言え、配偶者だったり、長女など他の兄弟からは不満が出てくることもあるでしょう。
そこで、他の相続人は遺留分請求をすることで、一定の相続財産を取得することができるシステムが国の法律であります。
しかし財産を残す人からすると、特定の人に財産を集中させたい場合もあります。
どのようにすれば法律をくぐり抜けられるのか考えるところですよね。
遺留分の相続生前対策について徹底解説!

どうしても大切な長男に、長女に、お子様に、配偶者様に財産をがっぽり渡したい場合はどうすればいいか、一緒に考えてみましょう。
その気持ちはとても理解できますし、人間ならば情というものは必ずあります。
早期の生前贈与
まず早期の生前贈与を考えてみてはいかがでしょうか?
状況によっては遺留分を全く認めないということも出来ますので、ご自身でしっかり考えていきましょう。
まず遺留分請求の対象となるのは、贈与と遺贈の2つになります。
贈与とは、単純に財産を渡すことですね。
遺贈というのは、遺言書で財産を引き継がせることですが、遺留分を計算する上で必ず対象財産となってきます。
贈与と遺贈によって、特定の相続人が多くの財産を取得することになると、他の相続人からの不満は確実に出てくるので、遺留分の問題になります。
特にお金絡みは問題になりかねません。
遺留分の問題が出てくるというものの、生前贈与という抜け道があります。
生前贈与は全てが遺留分の対象となるわけではありません。
一定の期間制限が設けられており、その期間内に行われた贈与が遺留分の対象となります。
ですので、期間外の贈与は遺留分の対象とはなりません。
早期の生前贈与が遺留分対策に効果的になるのではないでしょうか。
相続人に対する贈与
まず1つ目は、相続人に対する贈与についてです。
相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にされたものに限り、遺留分の対象となります。
・事業のお金
・自宅を購入するお金
・一部の不動産の譲渡
などといった、扶養の範囲を超えた資金的援助をしてしまうと遺留分の損害にみられてしまうケースがあります。
基準としては、扶養の範囲を超えた資金的援助が、相続開始前10年以内に行われているといったところになりますね。
例えば、亡くなる12年前に長女Aに自宅の購入資金として2,000万円の贈与をしていたケースで考えましょう。
10年以上経っていますので、遺留分の対象から外れます。
親が亡くなった際に仮に遺産がゼロであったとしても、遺留分請求はできないことになります。
かなり前の段階から資金的援助をしておくと良いことがわかりますね。
相続人以外のものに対する贈与について
2つ目は、相続人以外のものに対する贈与です。
なかなかないケースかと考えますが、たまにそういった方もいます。
例えば、長男の娘は相続人ではなく、相続人以外のものに当てはまります。
意外と言われてみれば身近なケースでもありますよね。
相続人以外のものに対する贈与に関しては、相続開始前の1年間にされたものに限り、遺留分の対象です。
亡くなる2年前に長男の娘に2,000万円を渡していても、基本的には遺留分の対象とはなりません。
遺留分の相続生前対策として、とても効果的な方法ではないでしょうか。
遺留分の対象外となる贈与
まとめますと、相続人に対して贈与する場合には、
・相続開始から10年以上前の贈与
・相続人以外は1年以上前の贈与
であれば良いということがわかります。
ここで一つ注意点があります。
例えば贈与する父親と長男が、次男や妻などに損害を与えることを知っていながら行った贈与に関しては、期間の問題ではありません
確実に故意になりますので、法律上遺留分の対象になるとされています。
しかし、父親と長男の意志を法的に立証するのは、かなり困難だと考えます。
もちろん遺留分を請求する人が申し立てていくのには間違いありませんが、時間が立つにつれて、もっと厳しくなるでしょう。
そして、人の死期を確実に予測することはできませんよね。
ですから、できるだけ早く贈与を大切なひとにしておいた方が良いのではないでしょうか。
生前贈与と相続放棄の利用について
2つ目は、生前贈与と相続放棄を利用する方法です。
このケースは聞く限りでは、1番よく取られているケースかもしれません。
放棄した人への生前贈与は相続人以外への贈与として扱われるようになりますよね。
贈与が亡くなった日から1年以上前のものであれば、遺留分の対象にならないことがわかるでしょう。
ここでも故意があるか立証できるかどうかの問題になってきますが、基本的に立証は難しいです。
とはいえ、100%遺留分請求が認められる可能性はないとは言いきることはできませんので、そこはご自身の判断でお願いします。
相続放棄と早期に生前の贈与を行うことにより、このようなメリットも出てきますね。
生命保険の活用について
3つ目は、生命保険の活用です。
十分な現預金があるような場合には、生命保険を活用しましょう。
生命保険金というとあまり良くないイメージもありますが、メリットもあります。
・相続税の節税効果も見込める
・遺留分対策としても活用することができる
生命保険とは、主に終身型の死亡保険のことです。
CMなどで加入のおすすめがよくある、被保険者が亡くなられた際に受取人へ保険金が支払われるものを生命保険と言います。
生命保険の保険料は毎月支払う方法や一括で保険料を支払う一時払いの方法が選べるようになっています。
これを相続対策として検討する場合は一時払いで現預金を保険金として扱うイメージですね。
保険会社が儲けているのではないかと思われる方も多いと考えますが、死亡保険金には大きなメリットが存在します。
それは、死亡保険金は相続人固有の財産であり、相続財産として扱われないということです。
相続財産とされていませんので、遺留分の対象ともなりません。
遺産分割をせずに受け取ることが可能です。
もちろん受取人が指定になっていますので、保険証書を持って一人で受け取りましょう。
相続人同士で揉めなくて済むところがいいですね。
贈与したい人の独断で決められるところも理にかなっています。
例えば、あなたに5,000万円の預金があったとします。
相続人が子Aと子Bの場合は、それぞれの遺留分は遺産に対して4分の1です。
5,000万円をAに全て相続させる遺言を残すと、Bは遺産に対して1,250万円の遺留分があることになります。
ここで、3,000万円の生命保険に加入すると、相続人の財産は2,000万円になりますので、遺留分は1,000万円まで減らすことができます。
1,000万円をAに全て相続させる遺言を残すと、AはBから遺留分請求されても結果的に4,000万円を相続できるということになります。
ただし、過度の保険の活用は、相続財産として扱われる可能性がありますので、注意が必要です。
しかし、このケースの場合は生命保険金の総額が、遺産総額に対して50%以上ありますので、相続財産として扱われる可能性もあります。
生命保険をかける時は十分に対策を練りましょう。
遺留分の生前放棄について
4つ目は、遺留分の生前放棄です。
遺留分の生前対策の一番確実な方法として、相続人と交渉して、遺留分を放棄してもらうことが挙げられます。
生前の相続放棄は法律上できませんが、遺留分は生前に放棄することができます。
ただし、遺留分の放棄を行うためには、遺留分を放棄する相続人が家庭裁判所の許可を得る手続きが必要になりますのでご注意ください。
被相続人の不当な圧力によって、不本意に権利を奪われることが無いようにということですね。
家庭裁判所では、相続人の意思を尊重してくれますので、相続人と交渉して自主的に遺留分の放棄の手続きを行ってもらう必要が出てきます。
しかしながら、被相続人も何もしないわけにはいかないのです。
例えば遺留分を放棄する見返りに、一定の財産を生前贈与するなどの遺留分に相当する程度の贈与を行う必要が出てきます。
非常に難しくはありますが、これら全てを踏まえた上で、遺留分を権利者自身が家庭裁判所に放棄の申立を行って、手続きを行うことで半分は解決します。
半分と書きましたが、あと半分は、遺言書を残すことです。
遺言書の作成についてはこちらの記事をご覧ください。
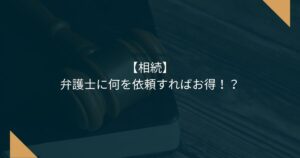
遺留分の放棄をしても相続人として、遺産を相続する立場は変わりません。
ですから、特定の相続人へ遺産を残す内容の遺言書を書きましょう。
養子縁組について
5つ目の遺留分対策は養子縁組です。
相続対策として養子縁組があります。
養子縁組によって相続人を増やすことで、各相続人の法定相続分が減ります。
それに応じて各相続人の遺留分も減少しますよね。
例えば、子CとDの場合に、それぞれの遺留分は4分の1ですが、Cの子1人を養子とすれば、相続人は3人となりますので、各相続人の遺留分は6分の1となります。
相続人の数が多いとその分、相続税を減らすことができます。
ですが、何人でも養子をとっていいわけではありません。
実子がいる場合は、養子は1人までと法律で決まっています。
実子がいない場合は2人まで養子として受け入れられます。
遺留分の生前対策を行う場合は、養子縁組は有効でしょう。
遺留分の相続生前対策をしてみましょう

遺留分の相続生前対策の5つの手法について解説してきました。
この記事を見て、ご自身ができる遺留分の生前対策からしていきましょう。
大切な人に大切な財産を残してみませんか?